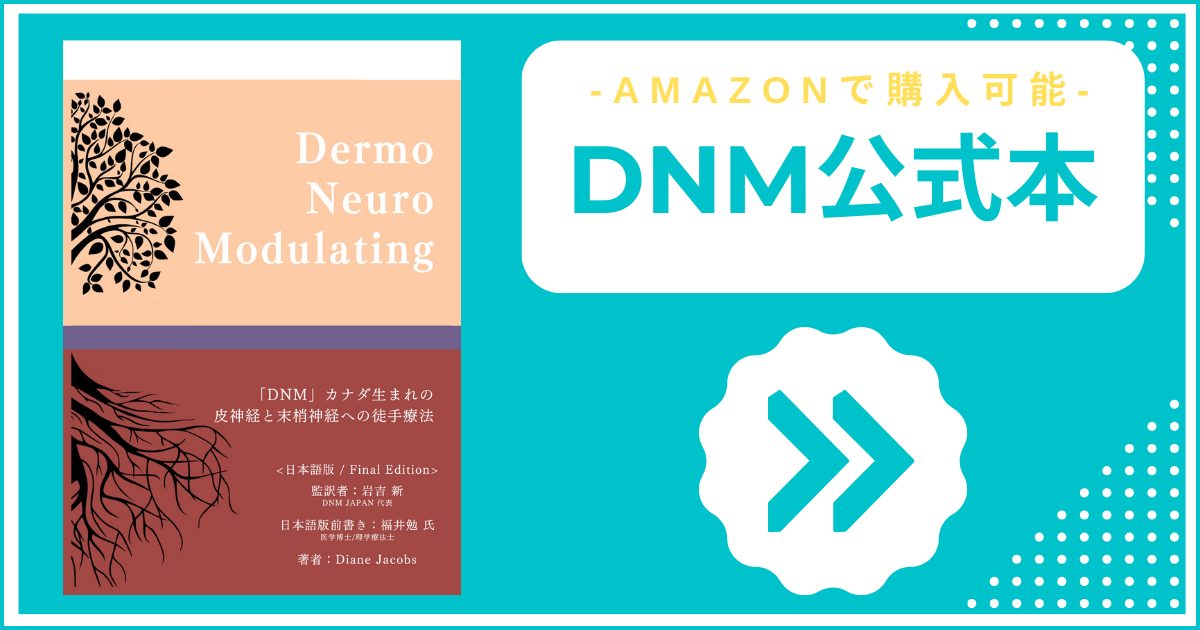神経筋リラクゼーションは
起こっていない。
等尺性収縮・PNF・MET
ストレッチ
神経筋リラクゼーションとは、神経筋の反射を使って緊張した筋肉を弛緩させたり、可動域を増やしたりする徒手の方法です。
理学療法の等尺性収縮後の弛緩アプローチ、PNF、MET/マッスルエナジーテクニックなどの理論/説明モデルでもあります。
その反射は、下記のようなものがあります。
伸張反射:
筋肉を伸ばすとその筋が反射的に収縮するという反射です。筋紡錘からのⅠa求心性信号によって起こり、同じ髄節の運動ニューロンを興奮させ、筋を収縮させるというものです。
静的ストレッチのときに伸張反射を起こさないようにゆっくり伸ばしましょう、などとよく言われています。
相反抑制・Ⅰa抑制:
主働筋が収縮すると拮抗筋が弛緩する反射のことです。 筋紡錘の感覚線維であるⅠa線維は、脊髄内で抑制性介在ニューロンに繋がり、拮抗筋の運動ニューロンを抑制して弛緩するという理論です。等尺性収縮後の弛緩、PNF、METなどでよく使われている説です。
自原抑制・Ⅰb抑制:
筋肉を伸張させると伸張反射により収縮すしますが、さらに強く筋を伸張させると、腱にあるゴルジ腱器官のⅠb線維という感覚線維が、脊髄内の抑制性介在ニューロンに信号を送り、同筋の収縮を抑制して弛緩させるという反射です。これも同じように等尺性収縮後の弛緩アプローチやPNFなどでも使われている説です。
しかし、色々な本にも書いてあり、昔から使われている仮説ですが本当に起こってるのでしょうか?
常識は非常識であり、真実は固定概念を覆すもの。
この神経筋リラクゼーションそれに当てはまる可能性があります。
下記論文では…
それらが見事に否定されています。
一つ目の研究では、静的ストレッチだけでなく、反動をつけるストレッチでも伸張反射は起きませんでした。
そして可動域が変化したとしてもそれは神経筋リラクゼーションによるものではないと言う結論が出ています。
◆研究1
「実験的な証拠は、これらの主張のいずれも支持していない。
伸張反射は、ミッドレンジにある筋肉のとても速くて短いストレッチ中に活性化し、短期間の筋収縮が生じることが示されている。
しかし、エンドレンジへのゆっくりとした長いパッシブなストレッチを受けた、無症状者のほとんどの研究では、ストレッチされた筋の有意な活性化は示されなかった。
バリスティックストレッチをシミュレートした研究でも、ヒトと動物モデルの両方で、筋の有意な伸張反射の活性化のエビデンスは示されなかった。
1回の「コントラクトリラックス」ストレッチ効果を評価した研究と、短期(3週間と6週間)のストレッチの研究では、ストレッチされた筋の有意な筋電図活動は検出されず、受動的なトルク/角度曲線の変化も認められなかった。
したがって、エンドレンジの関節角度の増加は、神経筋リラクゼーションによるものではない。」
Increasing Muscle Extensibility: A Matter of Increasing Length or Modifying Sensation?
Dr, Harrison
次の研究ではPNFストレッチによる可動域の増加には相反抑制や自原抑制は起こっておらず、関係性もないという結論が出ています。
◆研究2
「相反抑制や自原抑制などの神経生理学的要因は、PNFストレッチングによって達成された高い可動域増加には関与しないようである。
相反抑制は認められなかった。
拮抗筋収縮中の筋電図が抑制ではなく上昇したことを示しており、おそらく共収縮を表している。
また、自原抑制も認められず、期待された抑制つまり筋収縮後の筋電図値は低下しなかった。
PNFストレッチングのメカニズムに関するこれまでの神経生理学的説明は不十分であるように見える。」
Neurophysiological Reflex Mechanisms’ Lack of Contribution to the Success of PNF Stretches
Ulrike H. Mitchell, J. William Myrer, J. Ty Hopkins, Iain Hunter, J. Brent Feland, and Sterling C. Hilton
◆研究3
次の研究では、コントラクトリラックス、つまり等尺性収縮後の弛緩やストレッチで相反抑制は起こらず、逆に拮抗筋の共収縮が起こっているという結論がででいます。
「結果は、試験中のハムストリング筋電図活動の平均がそれぞれ主動筋コントラクトリラックスで8%、コントラクトリラックスで43%増加したことを明らかにした。
この活動は試験全体で減少しなかった。
したがって、ハムストリングがかなりの張力下にある間、これらの条件下で可動域の増加が達成された。
この研究では、コントラクトリラックスは膝伸展に対するアクティブなハムストリング抵抗を抑制せず、実際には、ストレッチ段階における拮抗筋の活性増加をもたらした。
最近の研究では、特定のストレッチテクニックによる股関節と足首の関節可動域の変化は、ストレッチされた筋肉の筋活動量に直接関係しない可能性があることが示唆されている。」
MUSCLE ACTIVATION DURING PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION (PNF): STRETCHING TECHNIQUES
LOUISR.OSTERNIGP,H.D.,RICHARDROBERTSONP,H.D. RICHARDTROXELM,.S.,AND PAULHANSENM,.S
次の文献でも相反抑制は起こらず、共収縮が起こっているという結論が書かれています。
◆参考文献より
「それは拮抗筋の筋電図の振幅および 収縮力の観察可能な低下をもたらす。
この反応は弱く、非-機能的で、 数ミリ秒しか続かない。※1ミリ秒=0.001秒
それは連続的に(持続的に)誘発され得ない。 さらに、相反抑制は研究現象であり、 実験室での研究中に観察される生理学的な人工物である。」
「…それは通常の運動中には起こらない。 通常の状況下では、相乗作用を持つ対の筋に対する制御は 同時的かつ中枢的に制御される。」
「それは、機械的受容器の刺激によって、 末梢からコントロールされない。
さらに、運動中、 相乗作用を持つ対の筋の共収縮がしばしばあり、 これは相反抑制がないことを意味する。 そのような共収縮は、 MET/ PNF活動期間中に証明された。」
「METの研究で、我々は 上腕二頭筋のマッスルエナジーテクニック中に、 上腕三頭筋が同時に共収縮することを証明することができた。
上腕二頭筋の収縮力が大きいほど、 上腕三頭筋の共収縮が大きくなる。 もし相反抑制が存在する場合、 上腕二頭筋収縮中に上腕三頭筋の筋電図活動が 見られなかったはずである。」
引用: Therapeutic Stretching/Laderman/ELSEVIER
◆結論
これらのことから、相反抑制や自原抑制や伸張反射は、日常生活では瞬間的に起こっている可能性はあるが、徒手やストレッチおいてほぼ起こってはいないということが分かります。
ですので、等尺性収縮後の弛緩、PNF、METで可動域が改善されたとしても、それは神経筋リラクゼーションによるものではない他の要素を考慮した方がいいと考えられます。
そしてここでもいつも通りの問題がありますが、これらアプローチの説明モデルには「神経系」が脊髄反射以外では含まれていないのです。
脳や末梢神経と皮神経はスルーされています。
サイエンスから読み解くと、常識が実は非常識だということが分かるでしょう。
本に書いてあるからとか、偉い先生が言ってるからとか、昔から先輩が言ってるからと鵜呑みにしないでください。
科学的な仮説は、常に刷新し続けていくもの。
自分で調べて納得いく理論でクライアント様の人生を向上させたくはありませんか?