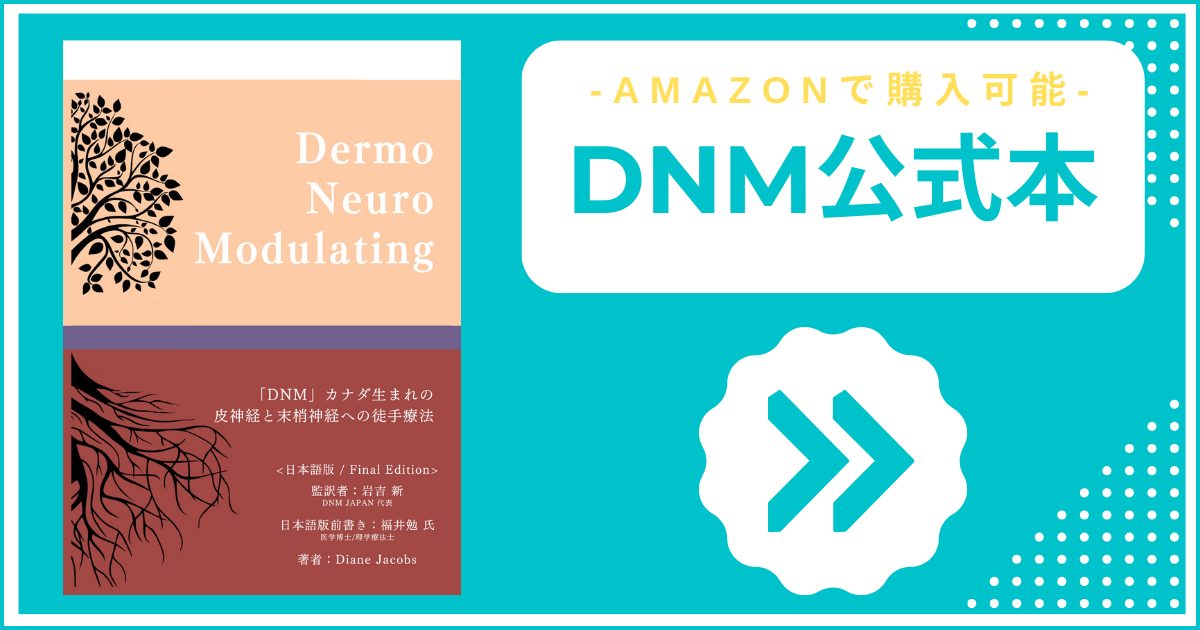筋膜アプローチを
サイエンスから読み解く。
◆筋膜のサイエンス
今までコラムにて、筋膜についてサイエンスからお伝えしてきました。
▷筋膜の歪み理論のエビデンスはない。
▷深筋膜を徒手では伸ばせない。
▷筋膜という結合組織を通常時より伸ばすという事は損傷させる事。
▷2Dのエコーでは筋膜の癒着を判別できない。
▷深筋膜を伸ばしても10cm程しか影響しない。つまりアナトミートレインのように遠くの筋膜に影響を及ぼせない。
▷ゾルゲル変化/チクソトロピーは、熱刺激がある間しか続かない。
▷痛みに対して痛み刺激を与え、一時的に痛みを減らす理論はDNIC。しかし侵害刺激に対して閾値が下がり、中枢が感作しやすくなります。
そして現在、日本の理学療法士・作業療法士の方々で学ぶことが多いのが、筋膜アプローチです。
◆筋膜アプローチとは?
筋膜が変性してコラーゲン繊維がねじれ、高密度化して水分が減り、基質がゲル状になってしまい、そしてコラーゲン繊維が癒着して、可動域の低下や痛みにつながる。
それに対して、深部の深筋膜に届くような強い圧力で、摩擦を起こして温度が高くなるように刺激をし、ゾル状態に変える。
そして、自由神経終末が解放され痛みがなくなり、さらに炎症を起こすことでリモデリングを起こし、その筋膜の癒着をなくし、正常化させるという理論とアプローチのことを言います。
高名な理学療法士の先生が行なっており、最近では筋膜リリースよりも有名になっております。

しかし、これらの理論はサイエンスから見て「ほんとう」でしょうか?
筋膜アプローチの文章を、一つ一つサイエンスから読み解いてみます。
◆サイエンスから読み解く
※引用文献: 筋膜マニピュレーション- 理論的背景と評価および治療方法 – 竹井 仁
「人は成長にしたがい,筋・筋膜のインバランスが生じ,さらに障害や外傷の既往からそのインバランスが複雑化する。」
→筋肉と筋膜に不均衡が起こるというエビデンスは見たことがありませんし、それがどのように問題になるのかも理屈が分かりません。またそれが可動域や痛みに関与するという根拠も見たことがありません。
「筋膜は様々な原因で変性する。外傷,廃用,循環不全による運動不足,反復運動,長期間にわたる不良姿勢などは,膠原線維束のねじれによって筋膜に高密度化を生じさせ,最終的に脱水が生じて基質を硬くゲル状にしてしまう。」
→筋膜は外傷や手術で瘢痕化することはもちろんありますが、運動不足や反復運動というレベルで、コラーゲン繊維がねじれたり高密度化するという根拠は見たことはありません。運動を全く行わない高齢者であれば筋肉や筋膜は癒着する可能性があります。しかしそれが痛みに繋がるという研究はありません。
もちろん脱水という概念も妥当性に欠けます。
「筋膜機能異常は,筋膜の高密度化,基質のゲル化,ヒアルロン酸の凝集化である。」
→一時的なゲル化や凝集はあり得ると思います。しかし、それ自体が筋膜の異常とまで言っていいかどうかは検討の余地があります。
「しかも局所に限らず,筋膜の配列を通して全身に広がることになる。」
→ 筋膜を伸ばしても10cm程度しか影響は及ばないという研究があります。つまり、アナトミートレインのように全身にその影響は波及しません。
「高密度化(基質がゲル状に変化し,ヒアルロン酸が凝集し,筋膜内コラーゲン線維の配列が変化)した筋膜に対して,摩擦によって温度の局所上昇を引き起こし,ゲル化された基質を流動化させることで正常な状態(ゾル)に戻し,筋膜の順応性を活用することによってコラーゲン線維間の癒着を除去することが求められる。」
→筋膜という結合組織は、手術や外傷がなく、高密度化&癒着するというエビデンスはありません。あったとしてもそれにより疼痛やROMの問題が出るという研究も見たことがありません。
また、ゾル・ゲル変化は、熱による一時的な変化であり、数分経てば元に戻ります。ゾルゲルの正常状態という概念も、生理学的に妥当だとは考えられません。
※ゾルゲル変化とは、チクソトロピーのこと。簡単に言うとゾルは粘性が低い液体で、ゲルは粘性が高い塑性固体のことです。
「深い圧を加え,熱をもたらすために筋膜に対して充分な時間の摩擦を与え,この熱は基質の粘稠性を修正し,治癒のために要される炎症過程がはじまる。」
→深部の筋膜に炎症が起こるということは、侵害受容線維が豊富な皮膚層にも損傷を与えているということ。
さらに、炎症後にはリモデリングによる瘢痕化/繊維化が起こるので、よりその局所が硬くなり、血流などの問題が起こりやすくなると考えるのが生理学的に妥当です。
「筋膜が修正され痛みが消えるまで,数分間実施する。」
→筋膜マニピュレーションは深筋膜の状態を変えようと摩擦を行うため、刺激が強く痛みを伴います。
つまりその数分間経つ間に、痛みで痛みを一時的に消すDNICが起こっているだけです。
※DNICとは、新しく侵害受容刺激を加えることで、新しい痛みに対してフォーカシングが起こり、元からある痛みを一時的に感じにくくなるという理論のことです。
またあまりに強い刺激だと、感覚線維が損傷したりして感覚鈍麻になっている可能性もあります。
「温度が上がると,ゲルがゾルへと変化して筋膜基質を修正する。高密度化の粘稠性の変換は,一般に数分以内に達成される。」
→熱によるゾルゲル変化は一時的です。当たり前ですがお風呂でも変化します。そして、数分で変化するということは、温度変化がなくなると数分で元に戻るということです。それを修正とは呼びません。変化です。
「突然,自由神経終末がリリースされることで局在部位が減少し,運動協調性の向上と正常化された関節運動の軌跡のために関連痛が減少する。」
→侵害受容線維が発火するような深い圧力刺激は、皮膚などにある自由神経終末である侵害受容線維を活性化させてしまいます。
つまり、炎症させているので自由神経終末のリリースどころか痛みが増えます。
※引用文献: 筋膜マニピュレーション- 理論的背景と評価および治療方法 – 竹井 仁
運動連鎖アプローチと普通のアプローチ | DNM JAPAN|最新ペインサイエンスをベースにした皮神経への徒手療法
◆考察
これらの考察から、筋膜マニピュレーションの効果は「DNICによる一時的な鎮痛効果」であるという事が分かります。
このように筋膜マニピュレーション理論においても、中枢を含めた「神経系の存在」は相変わらず無視されており、残念ながら組織のリリースだけしか視野に入っていません。
下記に再度まとめておきます。
▷筋膜の歪み理論のエビデンスはない。
▷深筋膜を徒手では伸ばせない。
▷2Dのエコーでは筋膜の癒着を判別できない。
▷深筋膜を伸ばしても10cm程しか影響しない。つまりアナトミートレインのように遠くの筋膜に影響を及ぼせない。
▷ゾルゲル変化/チクソトロピーは、熱刺激がある間しか続かない。
▷痛みに対して痛み刺激を与え、一時的に痛みを減らす理論はDNIC。しかし中枢が感作しやすくなる。
▷筋膜を炎症させてリモデリングさせると、治癒過程で瘢痕化が起こり、その部位がより硬くなる。つまり滑走性や可動域は低下する。
※詳しくは、「筋膜リリースについて」、「エコー下筋膜リリースについて」のコラムをお読みください。
今回の考察は、否定のための否定ではなく、徒手療法家を肯定するための否定です。
これはセラピストのためでもあり、最終的にはクライアント様や患者様の健康のための考察です。
既存の理論を鵜呑みにせず、認知バイアスに気をつけ、世界の最新のサイエンスによる考え方を身につけましょう。